 クマ美
クマ美今回から、経済的自由権を学習するわ!




判例が重要なんだモン。
本ブログでは、行政書士の試験科目「人権・経済的自由権」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
職業選択の自由
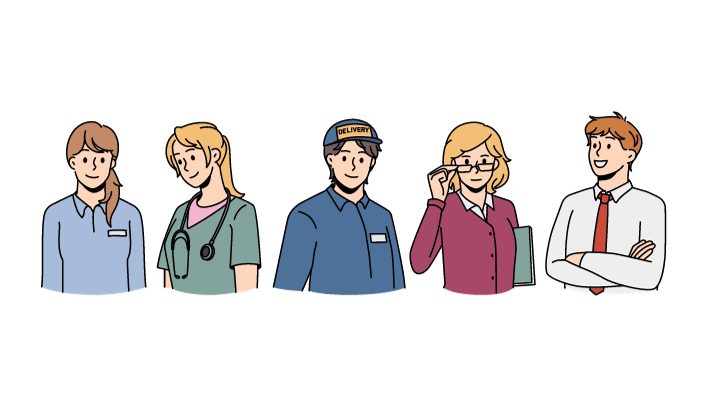
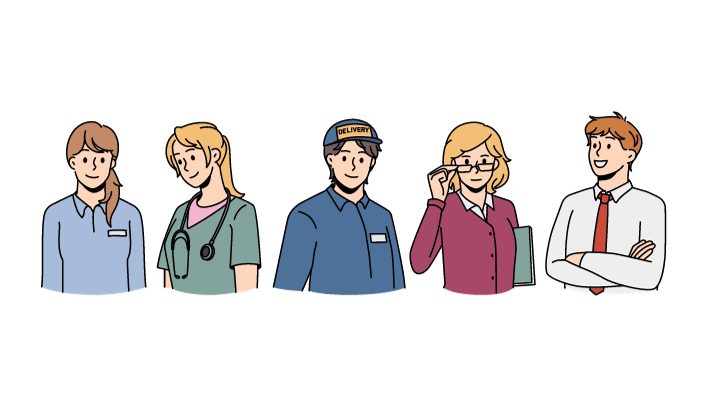
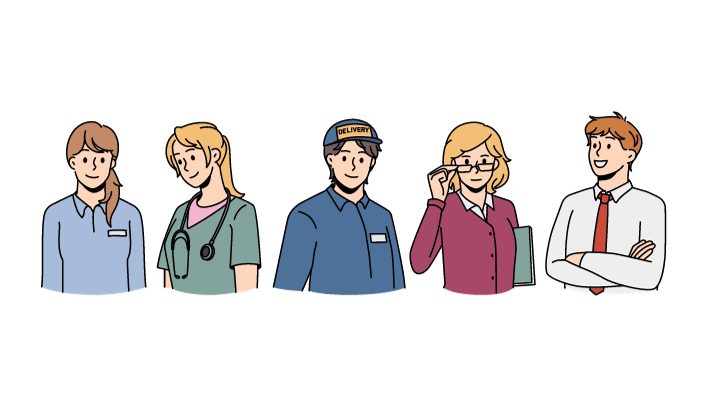
職業選択の自由とは、自分の職業を自由に決定できる権利のことです。
職業選択の自由に対する規制には、国民の生命・健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる消極的規制(警察的)と福祉国家の理念に基づき経済の調和のとれた発展を確保し特に社会的・経済的弱者の保護の竹に課せられる積極的規制(政策的)があります。
<事案>
小売商業調整特別措置法が、小売り市場の開設を許可する条件として適正配置の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
- 営業の自由の保障
憲法22条1項は、国民の基本的人権の一つとして、職業選択の自由を保障しており、そこで職業選択の自由を保障するという中には、広く一般に、いわゆる営業の自由を保障する趣旨を包含(ほうがん)しているものと解するべきであり、ひいては、憲法が、個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を一応予定しているものといえる。 - 公共の福祉による制約
しかし、憲法は、個人の経済活動につき、その絶対かつ無制限の自由を保障する趣旨ではなく、各人は、「公共の福祉に反しない限り」において、その自由を享有することができるにとどまり、公共の福祉の要請に基づき、その自由に制限が加えられることのあることは、憲法22条1項自体の明示するところである。 - 福祉国家的理想による制約
のみならず、憲法の他の条項をあわせ考察すると、憲法は、全体として、福祉国家的理想のもとに、社会経済の均衡のとれた調和的発展を企画しており、その見地から、すべての国民にいわゆる生存権を保障し、その一環として、国民の勤労権を保障する等、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策を要請している。 - 消極的規制と積極的規制
憲法22条1項に基づく個人の経済活動に対する法的規制は、個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が社会公共の安全と秩序の維持の見地から看過することができないような場合に、消極的に、このような弊害を除去ないし緩和するために必要かつ合理的な規制である限りにおいて許されるべきことはいうまでもない(消極的規制)。国は、積極的に、国民経済の健全な発展と国民生活の安定を期し、もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために、立法により、個人の経済活動に対し、一定の規制措置を講ずることも、それが目的達成のために必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、許されるべきである(積極的規制) - 小売市場の適正配置規制の合憲性
小売り市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企画するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置ということができ、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白とは認められない。
<事案>
薬事法及び県の条例が、薬局の開設を許可する条件として適正配置の規制を課していることは、憲法22条1項に違反するのではないかが争われた。
<結論>
違憲
<判旨>
- 職業選択の自由についての一般論
一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によって、提供すべき役務の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務づける等の強い規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合がある。 - 許可制自体の合憲性判定基準
一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のための必要かつ合理的な措置であることを要する。 - 消極的規制の合憲性判定基準
職業の許可制の合憲性を肯定するためには、それが自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的・警察的措置である場合には、許可制に比べてより緩やかな規制によってはその目的を達成することができないと認められることを要する。 - 薬局の適正配置規制の合憲性
薬局等の偏在→競争激化→一部薬局等の経営の不安定→不良医薬品の供給の危険又は医薬品乱用の助長の弊害という事由は、適正配置規制の必要性と合理性を肯定するに足りない。したがって、本件適正配置規制に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものであるといわなければならず、違憲である。
<事案>
公衆浴場開設許可の距離制限規定は、憲法22条1項に違反しないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
公衆浴場業者が経営の困難から廃業や転業をすることを防止し、健全で安定した経営を行えるように種々の立法上の手段をとり、国民の保険福祉を維持することは、まさに公共の福祉に適合するところであり、この適正配置規制及び距離制限も、その手段として十分の必要性と合理性を有している。
<事案>
酒類販売業の免許制が、憲法22条1項に違反しないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可性による規制については、著しく不合理でないものに限り、これを憲法22条1項の規定に違反するものということはできず、酒類販売業免許制度は、著しく不合理であるとまでは断定し難い。
居住・移転の自由



居住・移転の自由とは、自分の住所を自由に決定したり、自由に別の場所に移動できる権利のことです。
居住・移転の自由が確立した近代社会に移行して、はじめて資本主義経済の基礎が整うことになったという歴史的背景から、居住・移転の自由は、経済的自由権の1つとされています。
外国移住・国籍離脱の自由



外国移住の自由
外国移住の自由とは、外国へ定住するための海外渡航をする自由のことです。
国籍離脱の自由
大日本帝国憲法時代の国籍法では、個人の自由意思で国籍を離脱することは認められていませんでしたが、日本国憲法は、国籍離脱の自由を認めています。
財産権



財産権とは何か
財産権とは、自分の財産を自由に使う権利のことです。
29条1項は、私有財産制度を保障しているだけではなく、社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権につきこれを基本的人権として保障したものとされています。
財産権の制限
法律による制限
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定めることとされています。
これは、財産権については法律による一般的な制約が許容されることを明らかにしたものです。
<事案>
持分価格2分の1以下の共有者からの分割請求を禁止した森林法の規定は、憲法29条2項に違反しないかが争われた。
<結論>
違憲
<判旨>
森林法による分割請求権の制限は、立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれも肯定することのできないことが明らかであって、この点に関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超えるものである。
条例による制限
財産権の内容は「法律」で定めるものとされているので、条例により財産権を制限できるかが問題となります。
<事案>
奈良県ではため池の破損・決壊等による災害を未然に防止するため、ため池の堤とうに農作物を植える行為を禁止する条例が制定されたが、以前から堤とうを工作してきた被告人が条例制定後も耕作を続けたため条例違反で起訴された。そこで、条例による財産権の制限が憲法29条2号に違反しないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
- ため池条例の合憲性
堤とうを使用する権利を有する者の財産権行使がほとんど全面的に禁止されることとなるが、それは災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要から来ることであって、堤とうを使用する財産上の権利を有する者は何人も公共の福祉のため当然これを受忍しなければならないものであるから、ため池の破損・決壊の原因となる堤とうの使用行為は、憲法・民法の保障する財産権のらち外にあり、これらを条例で禁止・処罰しても、憲法及び法律に抵触も逸脱もしない。 - ため池の保全を上程で定めることの可否
事柄によっては、国において法律で一律に定めることが困難又は不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに条例で定めることが容易かつ適切であり、ため池の保全の問題は、まさにこの場合に該当する。
それではまた次回。













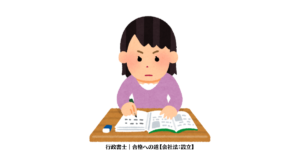


コメント